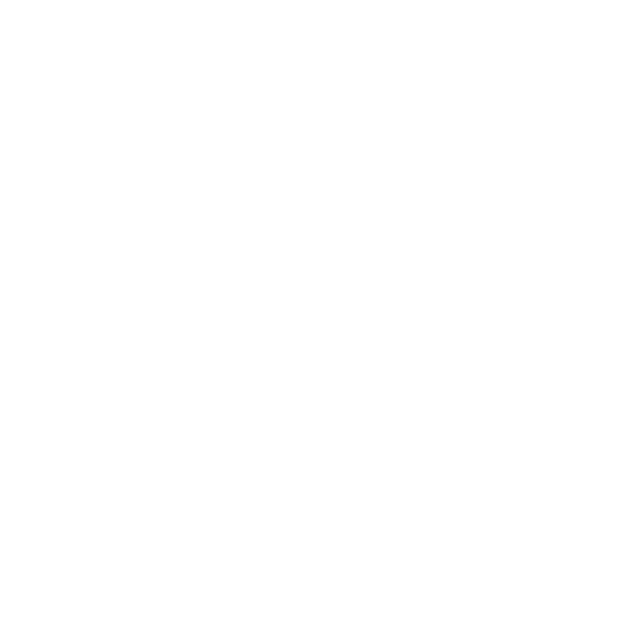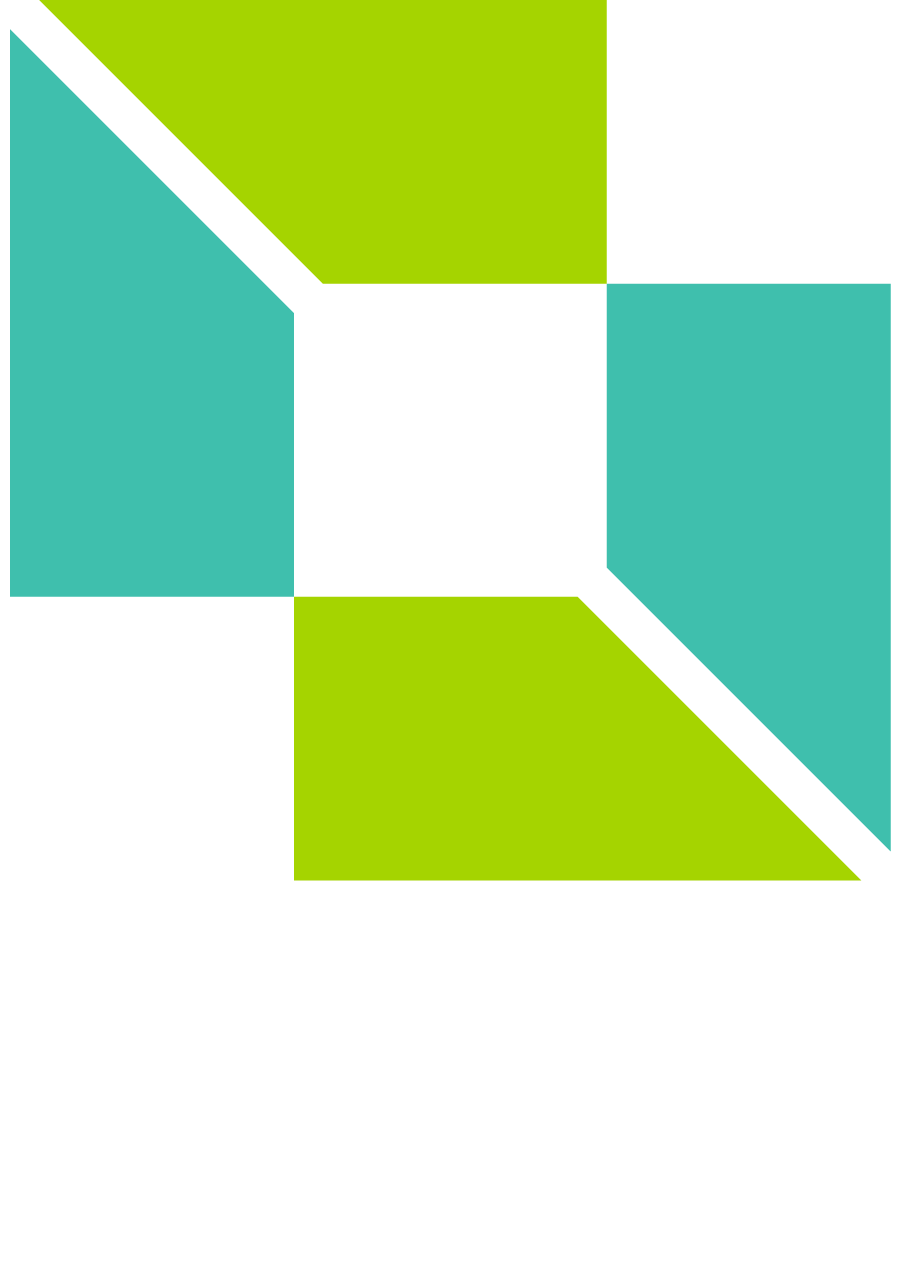アクティブラーニングは学生が主役~その4~
国際学部の竹澤伸一教授による「アクティブラーニング」コラム第4回。竹澤先生は授業の「主人公」である学生に自ら歩み寄り、発言を促し、主人公の意見に耳を傾けます。学生数が少数であれ多数であれ、その方法に変わりはなく、常に学生の発言を重んじて授業を進行しています。
「机間指導」という言葉をご存知でしょうか。小・中・高等学校で「授業」をおこなった経験のある方なら、おなじみの言葉です。「授業」中、基本的には座っている児童・生徒の間を巡回しながら、課題の進行状況をチェックし、個々に助言をする形式の指導のことです。当然、教壇から降りなければなりません。教壇と黒板(白板)にしがみつき、そこを「棲家」としている教員には、思いもよらない指導法です。教師が教壇から「降りる」のは、「主役」である学生に一歩でも近づくためです。「授業」の冒頭に、課題である予習レポートをチェックします。「授業」の中盤に、議論の対象になっている事柄に対して学生が取っているメモをチェックします。私は150人を超える大教室でも必ず、「主役」である学生のもとに「降りて」いきます。教師と学生の距離が近いと、学生は安心して発言してくれます。「机間指導」で個々のチェックを済ませているので、「発言するだけの準備」を学生がしているのが、手にとるようにわかるのです。学生を「主役」にするためには、教師が「降りて近づく」ことが必須です。名商大に赴任して、1コマ100分の「授業」を381回実施しました。どの「授業」も思い出深いものになっています。自分が何を教えたかより、「主役」である学生が何を表現したかを鮮明に覚えています。だから常時開放している研究室に学生が訪ねてくると、「授業」中の彼らの様子がよみがえります。「君はあの時こんな発言をしたよね。」と切り出すと、彼らは目を丸くします。私の「授業」と研究室にリピーターが多いのは、たぶんこのせいだと思います。
381回の「授業」で、私はマイクをただの一度もつかったことがありません。剣道と歌唱で声を鍛えてきたせいか、中学校の体育館規模でもノーマイクで相手に我が声を届けることができます。問題は中規模以上の教室で、学生の声を拾う時の工夫です。先天的に声の小さめな学生は必ず存在します。学生同士の議論の際、相手の声が届かないと致命的です。そこで私は学生のマイク代わりになります。挙手した学生のもとに飛んで行き、ささやくように発言する学生の発言内容を要約して拡声します。その時、その学生は、心の中で手を合わせています。そして次の発言の際には、声がほんの少し大きくなり、大抵にっこりします。こうした「主役」の成長を見るのも「授業」の楽しみです。

 過去問題
過去問題
 イベント
イベント
 入試情報
入試情報
 ネット出願
ネット出願