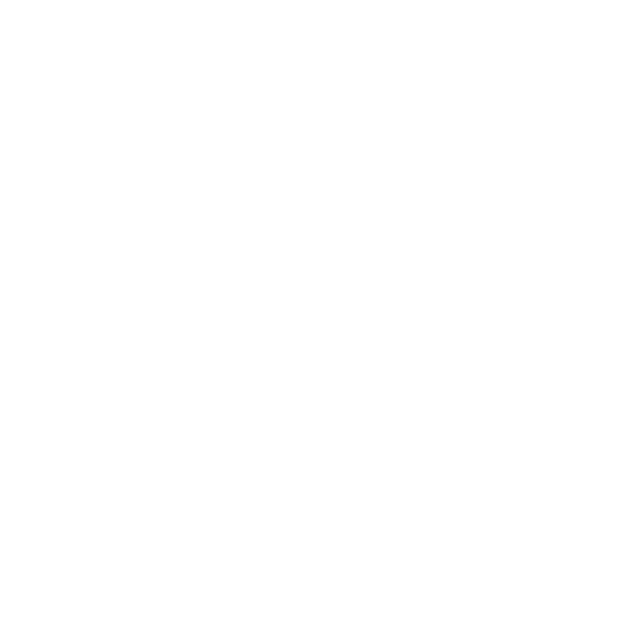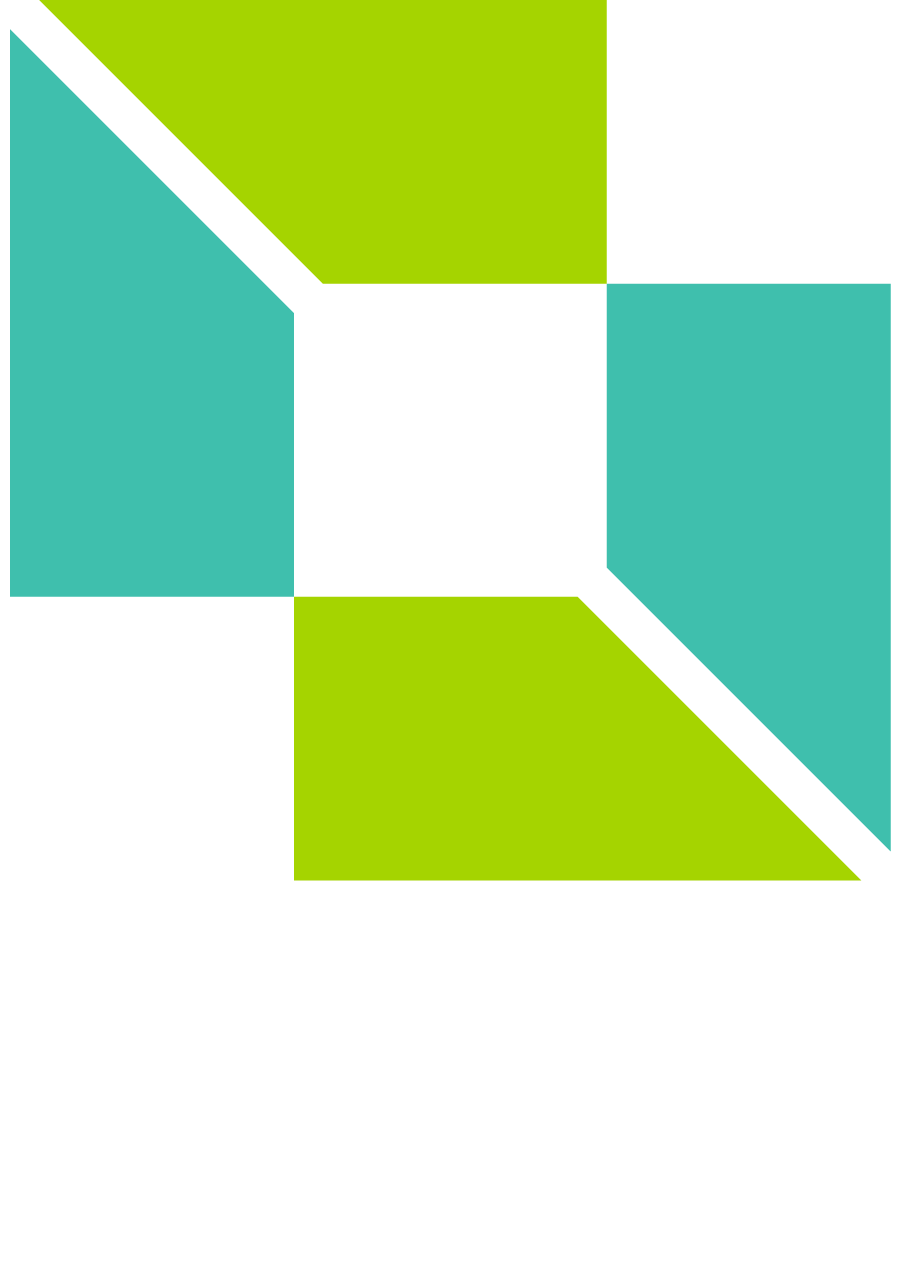商学部では何を学ぶのか?《商学部の意味と魅力》
商学部とは「専門力」「実践力」を磨く場所
商学部とは何かを理解するためには、商学とは何かを理解する必要があります。商学とは企業が行う商売を支える仕組み、すなわち商い(あきない)について研究する学問を指します。商学の歴史は古く、1904年という説(経営学部は1949年が国内初)があるくらいです。商学の歴史はともかく、商学とは、マーケティング、販売、流通、広告、簿記、会計、税金といった言葉は誰もが聞いたことがあるかと思いますが、商い(あきない)、換言すれば、ビジネスに関わる実践的な学問といえます。このように商学部は、商学を通じて、「専門力」「実践力」を磨くことを目指しています。
商学部の魅力
実務に直結した学びと職業資格の支援:商学部にはマーケティングや物流、商品開発などの実践的なビジネススキルを学ぶとともに、税理士や公認会計士などの職業資格取得に必要な知識を体系的に学べる環境が整っています。これにより、より高度な資格取得を目指す学生にとって最適な学びの場となっています。
消費者視点を重視した実務的な学び:商学部は企業活動が消費者にどのように価値を提供し、信頼を築くかを中心に据えています。消費者心理や購買行動の分析を通じて、製品やサービスの市場での成功を支援する具体的な方法を学ぶことで、資格を活かしたコンサルティング業務や実務での応用力を強化します。
伝統的な学びと最新ビジネス:商学部では、流通や物流、販売管理などの伝統的な商い(あきない)の基本を学ぶ一方、デジタルマーケティングやフィンテックなどの現代的なビジネスモデルにも対応。過去から未来へと続く商業の流れを理解することで、幅広いビジネスの可能性を探求できます。
商学部は、実践力と資格取得支援を組み合わせて、ビジネス現場での即戦力となると同時に、資格を活かした多様なキャリアパスを提供する独自の学びの場です。
商学部の英語表記は?
商学部の出身であることを示す英語表記は、商学部の英語名である「Faculty of Commerce」あるいは「School of Commerce」と表現する以外に、以下のように卒業時に取得した学位の英語表記名を示すことが一般的です。
- Bachelor of Commerce(BCom)
- Bachelor of Science in Commerce(BSc in Commerce)
- Bachelor of Arts in Commerce(BA in Commerce)
経営学部と商学部の違い
商学部と経営学部の違いは、経営学が企業(組織)運営に求められる視点(ヒト・モノ・カネ)を網羅的に学修することが求める一方で、商学部は企業活動その中の特定領域に焦点を当てて「深く学ぶ」姿勢を求める点にあります。具体的には商学部ではモノの動きに焦点を当てた「マーケティング」とカネの動きに焦点を当てた「会計」そして「ファイナンス」という3つの側面から、商学を専門的に学ぶことになります。
商学部で学ぶ領域
商学部ではビジネスについて、まずは基礎から一通り網羅する形で学びます。その上で、「マーケティング」「会計」「ファイナンス」について、より専門的に学んでいきます。
- マーケティング
- 会計
- ファイナンス
会計、マーケティング、ファイナンスの関係
「ファイナンス」で資金を集めて、「マーケティング」でお客さまが欲しいと思うモノを提供するのがビジネスの眼目です。両方がうまくいかない限り、ビジネスの成功はありません。そして「会計」は、会社の通知表(成績表)です。会社の健康状態を把握するためのもの、という言い方もできると思います。会社の状態を理解することができないと、何を目指して、どうやってビジネスを展開すれば良いのかが分からないので、ビジネス上の職務を全うすることが困難になります。ルールを知らずにゲームに参加するようなものです。このように「マーケティング」「会計」「ファイナンス」の3分野は、ビジネスを成功させる上で必須事項となります。
商学部を構成する代表的な学科
上記の学習領域にあわせて、商学部には1)会計学科、2)マーケティング学科、および3)ファイナンス学科が代表的な学科として設置されることになります。2と3を合わせて会計ファイナンス学科なるものも存在しますが、会計とファイナンスは異なる学問領域ですので「会計・ファイナンス学科」と表記すべきでしょう。因みに「ファイナンス」に関しては、下記のような2つの領域で構成されているので、もし同一大学の経営学部や経済学部で扱われる可能性が高くなります。
ファイナンスの分類
- マーケットファイナンス(資金運用)>経済学部
- コーポレートファイナンス(資金調達)>経営学部
商学部の教育に向いている人の特徴
インターンシップ参加
商学部の学生は「インターンシップ」に積極的に参加する傾向にあります。「キャンパス(机上)での学び」と、「企業の現場でのインターンシップ(就業体験)」を結びつけて、4年間、実践的な学びを経験できます。実際の広告業務、販売業務、ブランド・マーケティング業務、会計業務、税理業務を体験することができます。学んだ知識を活用して課題を解決する力を磨いていきます。
税理士や公認会計士を目指す
税理士や公認会計士の資格を在学中に取得することを目指す専門コースが設置されており、同じ目標に向かって切磋琢磨する環境が整えられています。特に税理士の場合には、大学在籍中に2-3科目に合格し、大学院に進学して2-3科目の試験免除を受けて、税理士を最短で目指すことが可能な環境にあります。
マーケティングとは?
マーケティングの教訓として、「良いモノを作っても売れるとは限らない」もしくは「伝わらないモノは存在していないのと同じ」があります。マーケティングでは「売れる仕組み(=消費者が欲しいものを市場に送り出す仕組み)づくり」が重視されます。このようにマーケティングは、消費者との関わりが強く、「お客さんが存在するところにマーケティングあり」ということが言えるわけで、ビジネスでは必須です。加えて、いまの日本はモノが簡単に売れない時代です。こうした厳しい時代において、企業が存続・成長していく上で、マーケティングがますます重要になってきています。「マーケティングの時代」といっても過言ではありません。
- この会社の顧客は誰なのか
- 顧客のニーズをどのようにして探り出せばよいのか
- 顧客にとって価値のある商品・サービスをどのように開発すればよいのか
- この商品を幾らで売れば良いのか
- 自社の商品・サービスの魅力を広告でどのように伝えていけばよいのか
- インターネットの仕組みをマーケティングにどのように活用すれば良いのか
そして今やマーケティングの対象は、企業に限ったことではありません。下記のようなマーケティングがあり、あらゆる組織と個人にマーケティングが関わるようになりました。マーケティングは、顧客(市民・患者・学生等含む)目線で見ていくモノの見方・考え方です。顧客との関わりを横断的に科学する専門分野です。それゆえ、キャリアを積んでいく上で、マーケティング(顧客目線で考える)は必須であり、全ての人のキャリア形成に資するものです。
- 国・地方自治体のマーケティング
- 学校のマーケティング
- 病院のマーケティング
- 非営利団体のマーケティング
- 個人のマーケティング
会計学とファイナンスとは
「会計」「語学」「IT」は、社会人が身につけなければならない「三種の神器」といわれています。「会計」のスキルや財務データから企業の業績を読み解く能力は、高度な専門職はもちろんのこと、一般企業においても必要とされています。「会計」は決算書を読むことからはじまります。決算書とは経営者にとっての成績表(あるいは患者の健康状態を捉えるカルテ)のようなもので、決算書が読めるとその会社の活動状況や実態が見えてきます。そして企業は資金を集めて機械設備や製品開発等に投資していきますが、このお金の流れが「ファイナンス」です。会計ファイナンス学科では、両者の密接なつながりを実践的に学ぶことができます。「会計」と「ファイナンス」の知識があってこそ、その全容をより深く理解することができるでしょう。
- この会社は売上高に応じた利益をあげているのか
- 高収益会社の利益の源泉はどこにあるのか
- この会社の巨額の赤字の原因は何なのか
- キャッシュ・フローは潤沢なのか
- この資産への投資は将来的にどれだけの利益を生み出すのか
- どのように資金を調達すればよいのか
商学部が得意とするケースメソッド教育
日本の大学の講義では、教科書を使って理論や公式を教員から学生に一方的に伝達する「レクチャー形式」の講義スタイルが一般的です。しかしながら名古屋商科大学商学部の講義ではアクティブラーニングの「ケースメソッド方式」を全面的に採用している点に特徴(違い)があります。ケースメソッドとは、実際に企業で起こったケース(事例)を使って対話形式で進められる講義手法のことです。具体的には、ケースを使って「この会社の成功要因は何か?」「この会社の強み(武器)は何なのか?」「この会社は今後どのような戦略を展開すべきか?」等々の実践的な問題を、議論を通して学んでいくことになります。
商学部の教育はそのミッションとして「フロンティア・スピリットを通して、グローバルで活躍できるリーダーを育成すること」を掲げています。相手の意見に耳を傾け、自分の意見をしっかりと主張する能力は、ビジネスリーダーにとって必須です。また、今の社会で必要とされる能力の筆頭にあげられるのが、「コミュニケーション能力」です。そうした社会的な要請を踏まえて、双方向型の、学生の主体的な学びを中心に据えた「ケース・メソッド方式」を商学部では展開しているのです。
商学部を希望する学生の立場にたってみても、ただ単に教室に座って、教員の話を受け身で聞いているだけでは、退屈してしまうかもしれません。学生が自ら講義に参加して、講義を作り上げていく醍醐味がケース・メソッドにはあります。学生の皆さんには、専門知識や理論を学ぶだけではなく、ビジネスについて語り合うことを通じて、コミュニケーション能力、問題解決力、洞察力、創造力、リーダーシップを身につけてもらいたいと考えています。
商学部と経営学部との違いは?
商学部と経営学部は、「専門性」と「視点」に関して、相違していると考えられます。
「専門性」による違い
商学部ではまず、ビジネスを基礎から一通り学びます。その上で、ビジネスで必須とされる「マーケティング」「会計」「ファイナンス」の3分野について、より重点的に、「専門的」に学んでいきます。「専門性を高める」というと、難しく感じるかもしれませんが、基礎から分かりやすく学ぶことを大事にしています。それに対して、経営学部では、ビジネスについて幅広く学んでいくことになります。それゆえ経営学部は、ジェネラリスト育成の場となっています。
「視点」による違い
商学部では、マーケティングに関してより深く学ぶことができます。マーケティングで大事なことは、「顧客が欲しいと思うものを市場に送り出す仕組みづくり」です。常に、「お客さんは誰なのか(Who)」「お客さんにどんな価値を提供するのか(What)」「お客さんにどのように届けるのか(How)」を考えます。それゆえマーケティングでは、「顧客目線」でビジネスを捉えることを重視します。それに対して経営学は、「経営者目線」で、会社の経営について学び、会社を経営するための能力を磨くことを重視します。マーケティングと経営学は、勿論、緊密に連携していますが、重視する「視点」が異なるということです。
商学部の就職先と就職実績
商学部では、専門的に学んだ内容を活かして、以下のような業種への就職が多くなります。
- 商社・物流・広告
- 監査法人・税理士事務所・会計士事務所
- 金融機関・証券会社
様々な就職支援行事を通じて、学生一人一人に対して、手厚いサポートを実施しています。したがって商学部では、実践的かつ専門的な教育や、ケース・メソッド講義を実践することで、社会で活躍するリーダーの育成に力を入れています。また、マーケティング分野の資格(販売士)、会計分野の資格(公認会計士、税理士、日商簿記)、ファイナンス分野の資格(ファイナンシャル・プランナー)取得も積極的に支援しています。その結果、商学部卒業生の就職率は97.5%(2013年度)に達し、内定者の約9割が「満足」のいく就職であったと評価しています。卒業生の就職する業界は、「流通業」、「サービス業」、「製造業」、「金融業」等、多岐にわたっています。「公認会計士」、「税理士」といった、会計・税務のスペシャリストとして活躍する人材も輩出しています。
商学部と関係の強い「税理士資格」
職業資格としては、税理士、会計士、ファイナンシャルプランナーの3つが商学部と関係性の強くなります。その中でも特に税理士に注目してみたいと思います。税理士になるためには税理士試験を通過しなければならないのですが、学部で商学部を卒業後に、ビジネススクール(大学院)に進学し、税法・会計に関する修士論文を作成することで税理士資格に必要な「5科目合格のうち最大3科目が免除」されるという制度があります。この免除制度を利用して商学部を卒業後税理士を目指す方は数多くおられます。
国内の商科大学《70年以上の伝統校》
経営学の起源とも言える商学を軸として設立された「商学系大学」は日本国内でも歴史が深く、東京商科大学(一橋大学)が国内最古となり、中部圏では名古屋商科大学が唯一の存在といえます。
- 東京商科大学(1920)現在の「一橋大学」国内初
- 大阪商科大学(1928)現在の「大阪市立大学」関西初
- 神戸商業大学(1929)現在の「神戸大学」
- 小樽商科大学(1949)
- 大阪商業大学(1949)
- 千葉商科大学(1950)
- 名古屋商科大学(1953)中部初
名古屋商科大学の商学部の特色
インターンシップ(就業体験)のプログラムが、他大学と比べて充実しています。とりわけ商学部では、「独自のインターンシップ先」を確保しています。それゆえ名商大が有するインターンシップに加えて、商学部独自のインターンシップに参加することが可能になります。「キャンパスでの学び」と、「企業の現場でのインターンシップ(就業体験)」を結びつけて、4年間、実践的な学びを経験し、就職活動を有利に進めることができます。その結果、名古屋商科大学の商学部は、中部地区でトップレベルの就職率を達成しています。また卒業後はMBAランキングで国内1位にランキングされたビジネススクール《大学院》に優先的に進学することが可能です。商学部独自の「税理士・公認会計士養成プログラム」も充実しており、合格実績も毎年積んでいます。

 過去問題
過去問題
 イベント
イベント
 入試情報
入試情報
 ネット出願
ネット出願