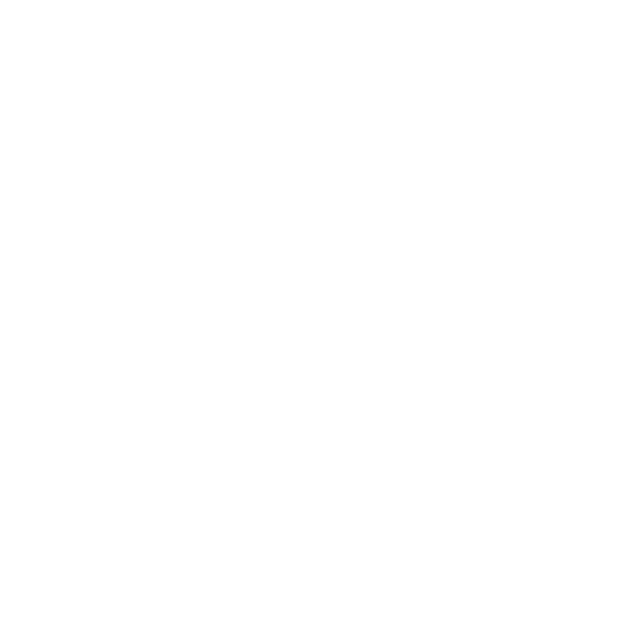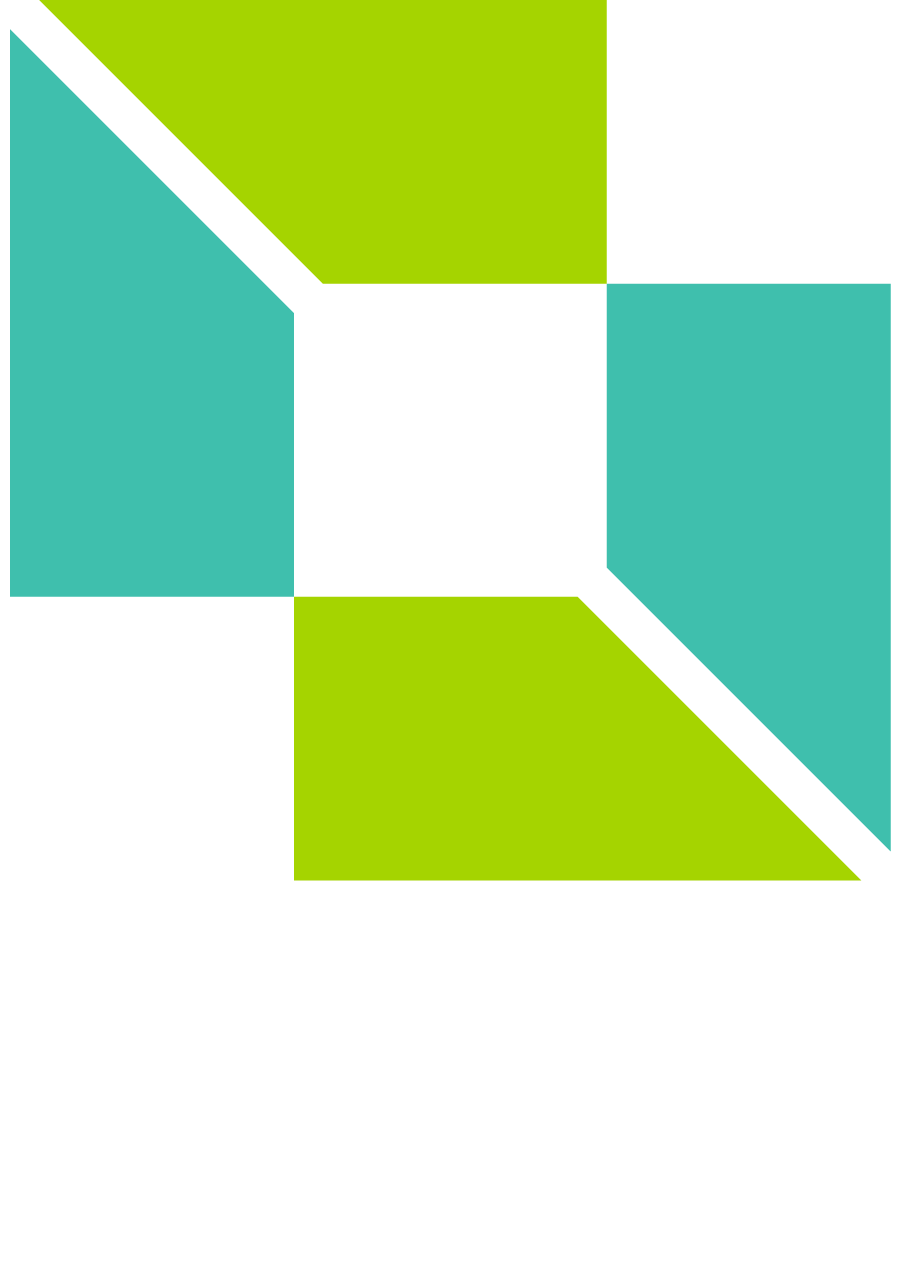科研費研究の紹介 Vol.1 ~経済学部 中西啓太 先生~
名古屋商科大学では科研費を取得して研究活動を行っている教員を取材し、その研究内容を公開します。今回はその第一弾です。これから数回にわたり連載予定!です。
教員・研究者の紹介
専門は日本近現代史。特に、国家と地域社会との相互作用、その間を媒介する地方行財政の働き、その周囲の地域経済や農村社会との関係に関心を持っています。
研究に活用する歴史史料を探すため、あちこちの文書館や資料館を回っています。また、古文書を所蔵するお宅にお邪魔し、整理や調査にも従事しています。
研究のテーマ
研究課題名「近代日本における地方行財政の転換と郡・町村の相互関係」
江戸時代の村落と現代の市町村は大きく異なる存在に思えますが、その間わずか100年ほどしか隔てていません。江戸時代が200年以上続いたことを思えば、急激な変化があったことが予想されます。なぜ、このような変化が可能だったのか、予想される歪みはどのように処理されたのか、そして現代にいかなる影響を及ぼしているのか、具体的には国家・地方行政機構・地域社会の相互関係を分析することを通じて考察しています。
特に注目しているのは、法律や政策が実行される場面での実態です。戦前日本の中央地方関係の特徴として、地方に政策・事務は行わせるが、財政制度は国庫優先で地方に制約がある、という行財政両面にわたる負担転嫁があったと言われています。
しかし、それではなぜ地方は大きな負担を耐えられたかというと、法律で決められた内容には、実は細かくも大きな裁量の余地があり、各地域の現実との間で摺り合わせが行われることが想起されます。その局面での柔軟性こそが、近代日本の歩みを支える強力な土台であったと考えています。この関係性が、日本の経済発展にあわせてどのように変化していくのか、地域間格差の発生や、企業・農村社会との関係の変化なども念頭に注目しています。
研究成果の普及
グローバル化が進めば進むほど、同時に「ローカル」の持つ重要性は高まると言われています。
しかしそれにもかかわらず、現代日本では、地方財政の窮乏化や地域間経済格差など、「ローカル」は大きな問題を抱えています。一方で、なぜこうした問題は生まれてしまったのか、その背景に対する認識はとても乏しいものではないでしょうか。そのような状況下で抽象的に地方分権化や地方創生と唱えても、果たして有効な対策となるのでしょうか。問題の淵源を実証的に探ることが対策の第一歩であり、本研究は着実にその真相に迫っていきます。歴史学はこうした基礎科学としての側面も持っています。
実際の講義への応用
歴史の講義は、現代とは大きく異なる社会のあり方を理解することで、異文化理解につながる力を養う意義があると考えています。
たとえば「日本産業史」では、経済発展の度合いがまったく異なる状況で、いかに経済社会が成り立っていたのか、理解することにつとめています。「地方財政論」では、現代の地方財政制度や中央地方関係がどのようにして形作られてきたのか、大きく異なるシステムがなぜ成り立ち、なぜ変化したのか、最新の知見も導入しながら、戦前と現代を比較する広い視点から講義を行っています。また、数値や歴史史料から情報を読み取り、意見を出し合う形の学習も重視しています。さらに、研究の進展により、高校までの学習や一般的なイメージとは見方が変わっていることがらも多く存在します。こうした視点の転換を理解することは、多様なものの見方を身につけることにつながります。
科研費とは
科学研究費補助金は全ての研究分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」を発展させることを目的とする研究助成金です。助成金は、相互審査(ピア・レビュー)を経て、独創的・先駆的な研究と認められた事業のみが採択されます。名古屋商科大学では科研費による研究テーマや実績について広く公表していきます。

 過去問題
過去問題
 イベント
イベント
 入試情報
入試情報
 ネット出願
ネット出願