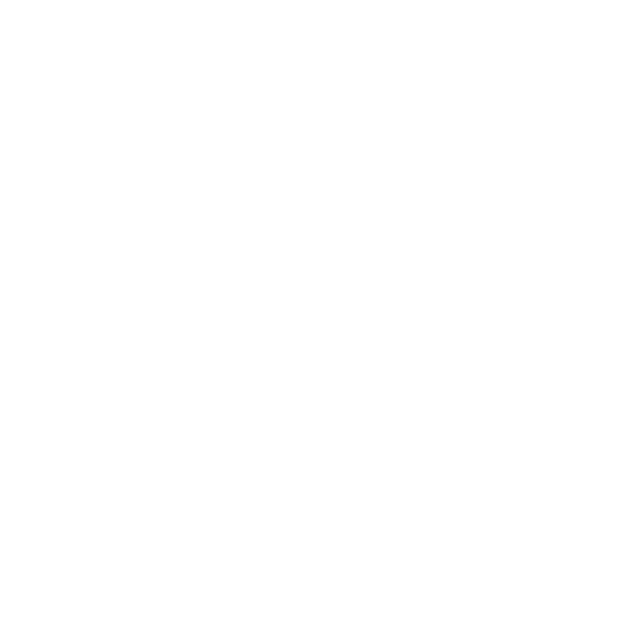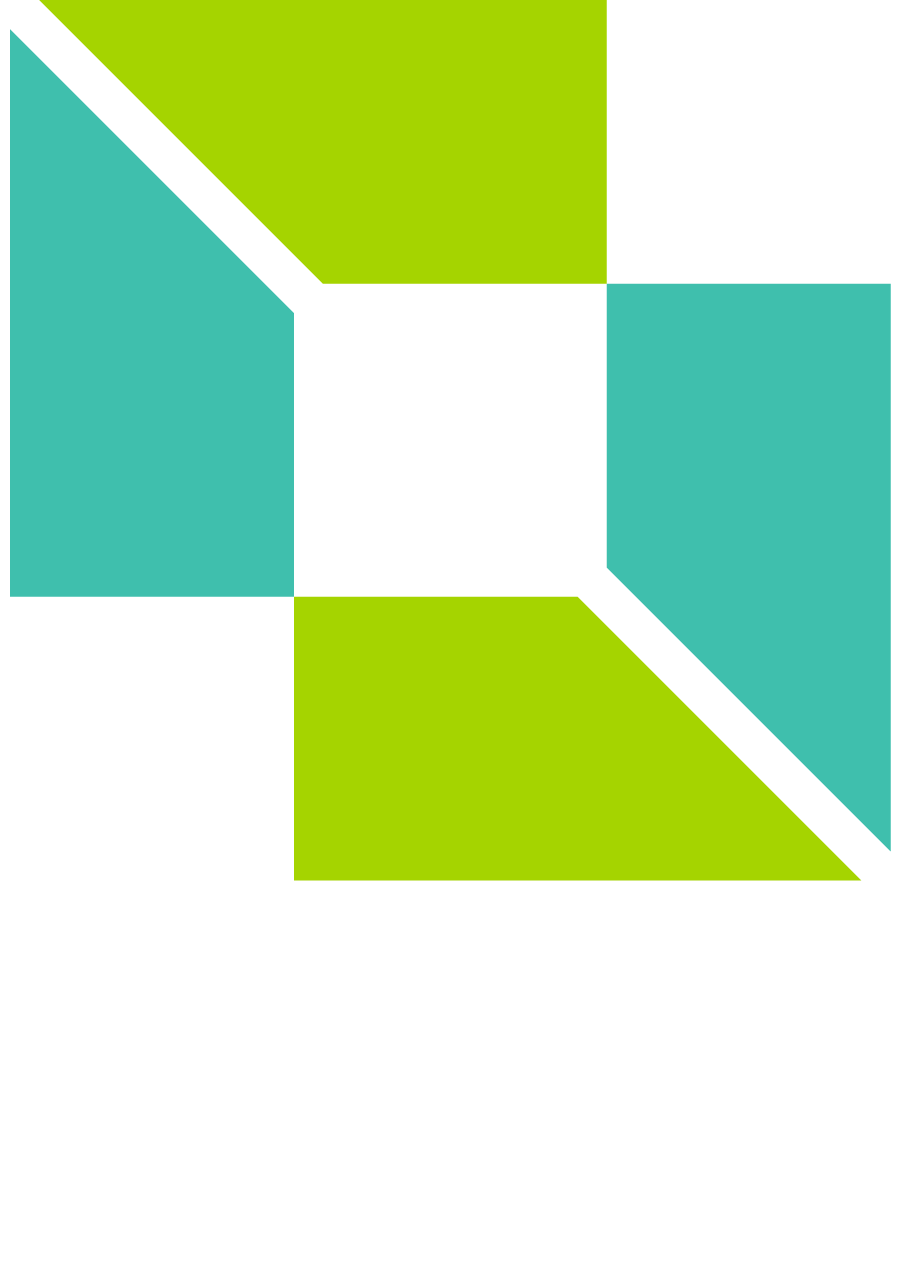国際学部では何を学ぶのか?国際学部の意味と魅力
国際学部とは何を学ぶ所か?
国際学部(英:Faculty of International Studies)とは、国際化した現代社会を生き抜くための教養を身につける教育課程です。現代の国際社会で必要とされるのは、多文化の環境で仕事を行う能力です。国際学では国際社会における相互理解を目標に、世界各地域の政治・経済、法律、言語、歴史などを修得。 世界の様々な国や地域の社会の実情を捉え、そこで浮き彫りとなった問題を多方向から理解できる人材を育成します。 また、国際企業や国際機関で活躍するため高度な語学力の修得も目指します。
国際学部と外国語学部の違い
現在、国内には37校の国際学部と31校の外国語学部が存在し、学問領域としてこれらの領域を部分的に扱う学校数はこの3倍以上存在します。
-
国際学部
37 校
-
外国語学部
31 校
外国語学部(英:Faculty of Foreign Language)とは、主に特定の外国語の習得と、その言語が使用される地域の文化や歴史、社会について深く学びます。例えば、英米語学科では、英語の習得に加え、イギリスやアメリカの政治、文化、文学、経済などを多角的に研究します。従ってこれらの違いを理解し、自身の興味や将来のキャリアプランに合わせて学部選択を検討することが重要です。
学習の焦点
- 国際学部 :国際的な問題や関係性を多角的に分析・研究
- 外国語学部:特定の言語とその地域の専門的な知識の習得
- 文学部 :文化、歴史、思想、文学を理解できる思考力を養成
目的
- 国際学部 :国際機関や多国籍企業などで活躍できる人材の育成
- 外国語学部:特定地域の専門家や翻訳・通訳者の育成
- 文学部 :文化や思想を深く理解した教養人や研究者の育成
国際学部で取得可能な学位と就職先
国際学部において取得可能な学位は大きく分けて「国際系」と「言語系」となります。卒業後の進路は、その語学力を活かして、外資系企業、海外事業部、貿易関連企業、国際機関、航空産業、観光業界、といった国際性の高い企業への進路希望が多いのが特徴です。
| 学士(国際教養) | 学士(国際文化) | 学士(英米学) |
| 学士(国際関係) | 学士(国際学) | 学士(外国語) |
| 学士(国際交流) | 学士(国際政治) | 学士(国際英語) |
| 学士(国際社会) | 学士(国際言語) |
国際学部の英語表記は?
正式には「Faculty of International Studies」もしくは「School of International Studies」となります。どちらを使用するかは、その大学の慣例や文脈に応じて異なります。
Faculty 主に使われる地域:イギリスやイギリス英語圏の国(ヨーロッパ、アジアの一部など)。例:Faculty of Science, Faculty of Arts, Faculty of Medicine。組織や学問分野の枠組みを強調した名称で、より伝統的、または正式な響きがあります。
School 主に使われる地域:アメリカやアメリカ英語圏の国(カナダ、オーストラリアなど)。例: School of Business, School of Engineering, School of Law。専門性や教育の実務的な側面を強調する傾向があり、現代的で親しみやすい響きがあります。
国際学部が高める能力とは?
国際学部では多文化や国際問題や国際関係などの理解を深め、国際社会で活躍できる能力を養います。そのためには、経済学、社会学、心理学、人間関係などを幅広く理解することが不可欠です。そして世界共通語というべき「英語」の運用能力を培うことは、国際社会で活躍するために不可欠です。しかしながら英語はあくまでも手段。英文法に「正解」が存在するかのような誤解も存在しますが、多文化社会においては「外国語」としての英語が共通語になっているので、現実的には「伝わる英語」を習得する方が価値があります。
国際学部を構成する代表的な学科
- 国際学科、国際関係学科、国際社会学科
- 英米学科、外国語学科、英語学科
英米学科で高める「英語運用力」
国際学部と呼ばれる教育課程では大きく分けて「英語教育」を担うカリキュラムと、多文化・異文化の環境で活躍するための力を養う「国際教養」を担うカリキュラムが存在します。前者の英語教育では語学運用能力を高めるための科目が能力別に体系的に構築されます。英語教育を担うのは言語学(Linguistics)やTESOLの専門家。TESOLとは、Teaching English to Speakers of Other Languagesの略で、英語を母国語としない人に第二言語または外国語として英語を教えることに焦点を当てた教育分野です。国際学部を選択する際は言語学やTESOLの専門家の充実度が目安になります。
国際学科で高める「多文化共生力」
例えば、今や国際都市として発展したドバイやアブダビなど、アジアや欧米とも異なる歴史文化を持つ中東諸国では天然資源による経済力を背景にリゾート開発が盛んです。日本人の常識感覚では思いつかないような発想で開発された都市は未来を想像させますし、一方で古き過去の姿も残しています。宗教的な要素が日常生活にも影響を与えている場合もあり、日本人の常識からすると「理解しにくい」側面もありますが、それはお互い様です。視点が異なるだけで、互いの文化を尊重する視点が重要であり、国際学部が目指す教育はこうした異文化への理解と異文化の方々との共生です。
多文化共生力とは?
異なる文化や価値観を持つ人々と協力しながら共存し、共に社会を築いていくための能力や意識を指します。この力は、グローバル化が進む現代社会において、ますます重要とされています。以下にその主要な要素を説明します:
- 異文化理解と尊重
- 効果的なコミュニケーション
- 協働と柔軟性
国際学部で多文化共生力をどう身につけるのか?
教室内での講義のみで国際感覚を高めることは限界があります。要は日本の外に出る「経験」を通じてしか国際感覚とのズレに気がつくのは難しいのです。そこで国際学部では、海外体験、海外留学、海外研修、海外ボランティア、といった体験を4年間の間に1つ選択し参加することでリアルな世界情勢や文化、経済を身をもって体験することを実現しています。必要なのは世界の人々や企業や社会が直面している課題を肌で感じ、理解した上で、的確な判断力をもって行動する「チャンレンジ精神」です。
国際学部は全員が海外体験
アメリカやイギリス留学は珍しくない昨今、国際学部が目指すのは単なる留学ではなく《海外体験》です。北欧、南米、アジアなど英語圏にとらわれず海外を肌で体験し、そこで得られた実体験を通じて得た国際的な思考を備えた人材を育成します。もちろん語学力も必要な要素ですが、中には英語力を必要としないプログラムも多数実施しています。本学が誇る海外トップレベルの大学への交換留学をはじめ、短期サマープログラムや、国際ボランティア活動、ヨーロッパ一人旅の「ギャップイヤー」など、数多くのユニークでサポートも充実した海外プログラムへの参加を提供します。そしてどうしても海外体験に参加できない場合でも、キャンパス内で実施されている交換留学生との合同講義で単位を取得することでも置き換えることが可能となっています。
国際学部生に人気の海外留学プログラム
- 国際ボランティア
- 海外インターンシップ
- 海外語学研修
なぜ海外プログラム参加前の「Language Exchange」が人気なのか?
海外留学前の準備としてお薦めするのが「Language Exchange」。学内留学ともいわれるこのプログラムはビジネスを学ぶ「留学生」と英語を学ぶ「日本人」がペアを組み、互いの言語を教え合いながら互いの文化や歴史の違いの理解促進を目的とするものです。国際学部ではこうした学内留学を1〜2年次で実施し、海外プログラムへの参加に備えていきます。以下では、本学でビジネスを学ぶ国際学生の声をご覧いただけます。
国際学部が提供する海外体験プログラム
短期型
1週間から1ヶ月間の期間で実施するプログラムとなり、夏季冬季の長期休暇を活用して実施することが通例です。
- イングリッシュキャンプ(滞在型英語研修)
- 海外スタディツアー
- 国際ボランティア
- 海外語学研修
- 海外インターンシップ
- 短期留学(夏季・冬季)
長期型
3ヶ月間から1年間かけて実施するプログラムとなり、その間の活動を単位認定しながら4年間での卒業を目指します。
留学プログラムの重要なポイント
留学プログラムには大きく二種類が存在し、授業料免除型と自費参加型となります。多くの国際学部が留学を前提としながら、高額な留学費用を別途徴収する場合がありますので要注意です。
- 交換留学(授業料免除)
- 自費留学
「自費留学」とはその名の通り、留学先の授業料を負担する形での渡航となりますので、その間の日本国内での大学は休学にして参加することになりますので、ほとんどの場合において4年間では卒業できなくなります(留学先での在籍期間を、大学卒業に必要な在籍期間として参入できない場合がほとんどです)。加えて休学中も在籍料が必要になる場合もありますので要注意です。
一方の「交換留学」とは、留学先の授業料が免除されるのみならず(「給付」という表現を行う大学もありますが「免除」の方が正確です)、留学先での在籍期間や取得単位も、日本国内の大学卒業に必要な期間や単位として参入できるようになっているので、無駄なく安心して参加することができます。
円安時代の海外留学は「交換留学」
一般論として、円安になると海外旅行の費用は上昇します。単純計算で、1ドル100と1ドル150では1.5倍の費用になります。しかしながら「交換留学」であれば必要な授業料は日本国内の授業料のみとなります。交換留学の場合には渡航先大学の授業料は大学間で「相互免除」されていることが一般的ですので、残る費用は「渡航費用」と「生活費」等となります。生活費に関しても、海外大学のキャンパス内の学生寮を使用することで日本国内の学生アパートとほぼ同額になってきます。さらには、渡航費についても大学が一部奨学金の形でサポートする大学も存在しますので、うまく組み合わせればそれほどコストは変わらないのです。
名古屋商科大学になぜ国際学部が必要なのか?
グローバル人材の育成 現代のビジネス環境における国際化の進展に対応し、異文化理解や国際的な視点を持つ人材を育成するためです。国際学部を通じて、学生は国際社会で必要とされる知識やスキルを身に付け、グローバルリーダーとしての基盤を築くことができます。
多様性の推進と学内国際化 国際学部は、留学生を含む多様な学生を受け入れることで、多文化環境を学内に提供します。学生は異文化交流を通じて新たな価値観を学び、国際的なコミュニケーション能力を向上させることができ、すべての学生にとって貴重な経験となります。
地域貢献とビジネス教育との相乗効果 名商大のビジネス教育の強みを活かし、学部から大学院まで一貫した教育を提供すると同時に、地域企業の国際化を支援します。卒業生は、国際機関や外資系企業で活躍する機会を得て、地域と世界の発展に貢献することが期待されます。
このように、単に英語運用力や国際社会の理解を深めるのではなく、「ビジネス」の感覚を高めることを通じて、これからの多様な国籍の人と共に働く、いわば「多文化共生社会」においてリーダーシップを発揮することが期待できます。以下は、経営教育において国際認証を取得した名古屋商科大学の持つ潤沢な海外ネットワークを国際学部が活用できる一例です。
| 名商大 | A大学 | B大学 | C大学 | |
| 留学生国籍数 | 74カ国 | |||
| 海外提携校 | 63カ国 | 36カ国 | 12カ国 | 8カ国 |
|---|---|---|---|---|
| 国際認証 | AACSB | なし | なし | なし |
国際学部の選び方
海外留学の際の「渡航先大学」の品質にこだわる
日本国内の国際学部の多くは海外留学を組み込んだカリキュラムが前提となっていますが「海外留学」とは個人で目的地を選択し、そこで何を修得するのか考え、事前の想定とのギャップに挫折を経験しながら、何とかなったという自信を片手に帰国して成長を遂げるものです。同一学年が一斉に同じ飛行機で同じ大学に海外留学するという大学も存在しますが、それは「ツアー旅行」であり修学旅行と変わりません。また海外には、何を根拠に「大学」と名乗っているか不明瞭な教育機関も存在します。したがって留学先教育機関の品質を「国際認証」の視点で峻別する必要があるのです。
大学としての国際認証の取得の有無
- AACSB(米国基準)
- EQUIS(欧州基準)
- AMBA(英国基準)
世界大学ランキングの視点
- THE Ranking
- QS Ranking
また世界の「大学ランキング」には、必ず在学生・教員の国際性に関する評価軸が存在しています。交換留学先として検討している大学がどのような国際性に関する評価を受けているか確認することをお忘れなく。
キャンパス内でも充実した国際交流が可能な環境を選ぶ
例えば本学では海外提携校から年間400名を超える国際学生を受け入れています。従って、キャンパス内はいつでも国際感覚溢れる雰囲気の中で学ぶことができます。また、定期的に彼らと交流できるイベントを開催したり、彼らの母国語と日本語を互いに教えあう「Language Exchange」を実施しています。交換留学生と一生の友になることで、将来的な国際的な協働が可能となり、世界で活躍できる基盤となります。
英語で学ぶ国際教養科目の拡充
英語で学ぶことのできるビジネス科目や教養科目を多数開講しており、交換留学生のみならず日本人学生も学ぶことも可能です。授業への積極的な参加が当たり前の留学生たちに交じって、一緒に学ぶことで、世界最前線のビジネスや教養を身につけることができるでしょう。
全国トップレベルの外国人教員の比率
外国人教員の比率が愛知県2位(全国11位)の本学では、常にネイティブスピーカーとコミュニケーションできる環境です。その他にも語学専門の学修施設である「総合語学教育センター」や、英語の自習施設「Self Access Center(SAC)」を備え、キャンパス内でもワンランク上の語学力を身につける環境を整えています。
国際公用語は何故英語なのか?
お互いに相手の言語が分からない状況で、コミュニケーションが必要な場面においては、人は無意識に共通言語を探そうとするものです。これは世界中、言い換えると地球で起こっていることですが、なぜ共通言語が「英語」なのでしょうか?理由は3つほどあるとされています。
歴史と経済の影響:大英帝国の植民地支配による英語の普及と、20世紀以降のアメリカの経済・軍事的台頭により、英語が国際的な基盤を築いたため
科学技術とビジネスの標準言語:学術論文、技術開発、国際取引の主要言語として英語が採用され、多国籍企業や国際機関でも広く使われているため
文化とインターネットの普及:ハリウッド映画やポップ音楽、インターネット上のコンテンツが英語を主流とし、文化的な影響を与えたため
英語を生かしたキャリアとは?
英語を生かした仕事をイメージすると英語教員、通訳や翻訳、観光ガイドなどが思い浮かぶかもしれません。しかし、企業での就職を考えてみてください。例えば、日本を代表する自動車メーカーであるトヨタは、世界中に支社や営業所を展開しています。そして、IT企業として有名な楽天は、既に2010年から社内公用語を英語に切り替えています。これらの企業は、グローバル展開や国際的な人材確保を目的として、社内公用語の英語化を進めています。
英語を社内公用語に採用している例
- ファーストリテイリング(ユニクロ):2012年3月から英語を社内公用語に統一
- 楽天:2012年7月から社内公用語を英語に統一
- 資生堂:2018年10月から本社部門で英語を公用語化
- シャープ:2023年から社内公用語を英語に移行する方針を示す
日本アニメの国際展開と英語の関係
日本の文化コンテンツの代表であるアニメ。今や世界中の外国人の日本語を勉強し始めるきっかけは、伝統的な日本文化への興味も去ることながら「ドラゴンボール」「ワンピース」「鬼滅の刃」「呪術廻戦」「ダンダダン」などなど。特に日本のアニメが世界配信される場合は、英語での先行配信が多く、直訳にならない英語ならではの翻訳が工夫されています。英語を勉強することは、英語を知るという事ことに留まらず、自身や日本を世界に発信するということに役立ちます。
国際学部を卒業した後の進路は?
国際学部を卒業した後の進路は非常に幅広く、国際的な視点を活かした多様なキャリアが考えられます。例えば、貿易会社や外資系企業での国際ビジネス分野、国際機関やNGOでの国際関係・外交の分野、観光業界でのホテルや旅行関連の仕事、さらには語学力を活かした教育職や翻訳・通訳といった道があります。また、大学院に進学して国際ビジネスをさらに深く学ぶことで、専門性を高めることも可能です。
国際学部はどのような人が向いているのか?
国際学部が向いているのは、1)多文化や異文化交流に関心があり、2)国際社会について学ぶ意欲のある人です。また、3)語学力を磨きたい、4)柔軟に新しい価値観を受け入れることができる、5)国際的な課題について考えることに興味があるといった特徴を持つ人には特に適しています。国際学部の大きな魅力は、語学力の向上や留学プログラムを通じて実践的なスキルが身につく点、多文化理解や国際問題を学ぶことで視野が広がる点、そして、さまざまな分野で活躍できるキャリアの選択肢が豊富である点です。さらに、国際的なネットワークを構築しやすく、留学や海外での経験を通じて自己成長を遂げることができるのもメリットの一つです。
国際学部と外国語学部の違いは何か?(続編)
国際学部と外国語学部の違いについては、その目的と学ぶ内容に明確な差があります。国際学部は、国際社会全体をテーマに扱い、国際問題や多文化理解、国際経済など幅広いトピックを学びます。一方で、外国語学部は特定の言語の習得や、その言語圏の文化や文学、翻訳や通訳技術の習得に重点を置いています。そのため、国際学部の卒業生は外交官や国際機関職員、国際ビジネスの専門家などとして活躍する一方、外国語学部の卒業生は通訳や翻訳者、語学教師などの職業に就くことが一般的です。言語そのものを深く学びたいのか、それを道具として国際的な課題に取り組みたいのか、自分の興味や目標に応じて選ぶのがよいでしょう。
学問の視点での違い
国際学部:世界の動向や課題に目を向け、社会科学や人文科学、自然科学など学際的な視点でアプローチ。「言語」はツールの一つであり、それを活用して課題解決に取り組む。
外国語学部:言語そのものを学問の対象とする。言語の構造や文化的背景、文学の分析などに焦点を当てる。言語の使い方だけでなく、その背景にある文化や歴史も重視。
キャリアの方向性の違い
国際学部:国際機関職員(国連など)、外務省、国際NGO、グローバル企業など。国際ビジネス、開発援助、観光業、ジャーナリズムなど多様なキャリアを目指す。
外国語学部:翻訳者、通訳者、語学教師、外資系企業の言語スペシャリストなど。言語スキルを活かし、専門職や教育分野で活躍することを目指す。
国内にある国際系の学部
- 国際学部
- 国際教養学部
- 国際ビジネス学部
- 国際コミュニケーション学部
- 国際文化学部
- 英語国際学部
- 国際関係学部
- 現代国際学部
- 国際社会学部
国際学部の魅力に関する解説
国際学部はどのような人が向いていますか?
国際学部では世界で活躍する人材の育成を目指します。つまり、言い換えれば、「将来、世界で活躍したい」と考えている人が、国際学部に向いている人といえるでしょう。もちろん、「外国に興味がある」、「英語をもっとしっかり学びたい」、「留学など国際的な経験がしてみたい」という考えを持っている人にも国際学部が向いています。なぜなら、国際学部では、英語能力を伸ばしながら、異文化コミュニケーションや世界の諸問題、国際問題への理解を深め、グローバル社会で活躍できる力を養うことができるからです。こうした力を身に付けたい、多角的な視野を持ちたいと考えている人が国際学部に向いているということができます。(国際学部:甲賀講師)
国際学科はどのような人が向いていますか?
上述の通り、国際学部では、英語能力を伸ばしながら、異文化コミュニケーションや世界の諸問題、国際問題への理解を深め、グローバル社会で活躍できる力を養うことができます。では、国際学科に向いている人というのはどういう人なのでしょうか。「国際」と聞くと、「英語」や「外国人」をすぐに思い浮かべる人が多いかもしれません。国際学科では英語能力を高めつつ、外国人との効果的なコミュニケーションについても学んでいきますが、より重きを置くのが、現在世界で生起しているさまざまな問題を直視し、その解決策を提言できる複合的能力を養成することです。つまり、よりグローバルな視点から国際的な問題を考えてみたい、多面的に考察して行動する能力を身に付けたいという人に国際学科は向いているといえるでしょう。(国際学部:甲賀講師)
英米学科の魅力
The charm of the Department of British and American Studies is that the curriculum emphasizes the improvement of English language proficiency as a communication tool for liberal arts education, cultural exchange, and future career goals. Students will study subjects dealing with business, cultural, social, and environmental issues and engage in case method discussions with foreign faculty members and foreign exchange students to improve their ability to communicate and develop an understanding of the world in English. As Japan becomes a more multicultural society in the future, cross-cultural understanding and mutual respect for different cultures are essential for young Japanese people as they become the leaders of tomorrow. English is also becoming more important in many business fields and industries in Japan, as English becomes the official language of business and trading, the sale of products and services, international institutions, and cross-cultural social engagements. Not only can students improve their English language skills by studying in the Department of British and American Studies, but they can also make meaningful friends with foreign students and develop professional international networks for the future.(国際学部:Townley教授)
インバウンド時代の国際学部の価値とは?
インバウンド(Inbound)とは「外国人が観光のために日本に来る」という意味で使われています。日本政府観光局(JNTO)の統計によれば、2024年の1月から10月までの累計は30,192,600人となり、1964年の統計開始以来、過去最速で3,000万人を突破しています。今後、訪日外国人観光客は増加の一途を辿るでしょう。このように国内市場の国際化が加速するインバウンド時代に国際学部で学び、期待される就職先は、外国人向けの国内観光の企画・案内業務を行う旅行業界に留まりません。ホテル業界の国際化対応、企業におけるガイドブックやチラシの作成、観光アプリの開発、百貨店やショッピングモール、アミューズメントパークでの外国人向けサービスや商品の企画、市役所や県庁など自治体での訪日観光客増加のためのマーケティングなど多岐に渡ります。(国際学部:磯野教授)
短期留学と長期留学どちらを選択すべきか?
それぞれのメリットを理解し、留学の目的を明確にして選択すると良いでしょう。短期留学のメリットは、大学の長期休暇を利用して参加できる点です。大学は夏季冬季に1ヶ月半から2ヶ月間の長期休暇があります。この期間を有効活用して短期留学に行き、集中的に語学力を磨くことや、国際ボランティアや海外インターンシップに参加して意義のある国際交流体験や海外での就業経験を得ることが可能です。長期留学のメリットは、語学力や異文化理解力の向上に加え、渡航先の大学で単位や学位を取得できる点です。外国語で専門知識を学んで得た単位や学位は、グローバル人材に求められる高い語学力やチャレンジ精神の証の一つとして、就職活動の際に大きなアドバンテージとなるでしょう。(国際学部:佐藤講師)
海外経験がない場合は、最初の留学は短期留学が良いかもしれません。特に初めての留学では、費用や手続き、渡航先での生活に不安を感じるのではないでしょうか。その点、短期留学は1週間〜1か月の期間で実施されるため経済的・精神的負担が少なく、留学ブログラムを終えたという達成感を短期間で得ることができ、自信につながります。自分の力で手に入れた自信は、帰国後の学業や進路選択に活かされるはずです。例えば、短期留学がきっかけで「議論や交渉ができるくらいに語学力を伸ばしたい」「海外で〇〇の仕事に就きたい」など、今後の目標が定まるでしょう。その目標達成のために、もう一度留学に行きたいと思うかもしれません。本学では複数回の留学が可能です。国際学部生の中には、短期の海外体験プログラムに2回行ったり、短期留学の後に長期留学に参加したりする人もいます。(国際学部:佐藤講師)
国際ボランティアに参加する意義とは?
国際ボランティアは、海外の若い同世代の人たちとボランティア活動を通して、異文化交流と地域貢献を実現するプログラムです。「ボランティア」と聞くと「発展途上国」などをイメージするかもしれませんが、ヨーロッパ、北中米、アジアの約30か国のうちいずれかへ行き、環境保護・整備、修繕・修復、建設・土木、子供たちとの交流、社会福祉などを行います。例えば、スペインでは伝統的なワイン製造の作業場作り、ドイツでは動物園の清掃・小屋のペンキ塗り、オランダではリサイクルショップ運営の手伝いなどが行われています。多国籍の参加者とともにこうしたプロジェクトに参加することで、異文化理解はもちろんのこと、リーダーシップや協調性、さらには国際的に通用する力を身につけることができます。観光で訪れただけでは決して得ることができない経験をぜひ味わってみてください。(国際学部:甲賀講師)
学内留学の価値とは?
学内留学とは、キャンパスにいながら、外国に留学しているのと同じ環境で学ぶことです。例えば英語圏に留学すれば、英語を話す学生に囲まれ授業を受けます。英語によるコミュニケーションが求められ、英語圏の文化を学ぶとともに自国(日本)の文化の独自性を認識し、その過程で異文化理解を体験します。国際学部ではアジアやアメリカにルーツを持つ学生が在籍しているだけでなく、ヨーロッパやアフリカ、オセアニア等出身の留学生と、定期的に図書館やカフェテリアで互いの言語を教え合ったり、ゲームをするイベントが開催されます。さらに多文化共生社会で生きるための多文化理解を促進する授業があるなど、キャンパスにいながら複数の外国に留学しているのと同様の、あるいはそれ以上の学びが期待できます。しかも、留学に必要な渡航や宿泊の費用を一切使わずに。(国際学部:栗原准教授)
国際学部を卒業したら何になれる?
国際学部に進学するメリットは、何といっても卒業後の進路選択に幅があることです。国際学部を卒業し、企業に就職をする場合は、おおよそ三つの選択肢があります。それは日本国内の企業、海外にある日本企業の支社(日系企業)、そして海外で現地企業に現地採用という道です。また、日本国内と言っても日本企業だけではありません。海外に本社があり、その支社が日本にという企業は数多く存在します。このように日本でも、海外でもという卒業後のグローバルな進路選択が国際学部の魅力です。そして、その就職も商社やメーカーといった企業だけではなく、行政機関や国際機関、教員、通訳・翻訳者など多様性に富んでいます。(国際学部:磯野教授)
国際学部のメリットとは?
国際学部は、外国語学部や文学部の英米語学科と異なります。外国語学部では「英語を学ぶ」のに対して国際学部では「英語で学ぶ」ということです。つまり学びは言語だけでなく、「多文化共生」や「国際社会」等に関する国際性を身につけるための科目が準備されているからです。1年次より英語科目に重点が置かれており、英語関連の科目はすべてEMI(English-Medium Instruction)、すなわち英語で授業が実施されています。さらに、その教材は主にビジネスに関わる内容となっているため、学んだことがすべて、実社会に出て企業等で活かせるわけです。国際学部の学生が就職活動で英語での面接試験に強いと言われる所以でしょう。(国際学部:栗原准教授)
なぜ海外経験が就職やキャリアに有利なのか?
海外経験がキャリアに価値を持つ理由として、異文化交流を通じて自己成長とスキルアップができること、それによって将来のキャリア選択の可能性を広げることができることが挙げられます。異なる文化や習慣を実際に体験することで、国際的な視野や思考を養い、他者を理解し尊重する力を高めることができます。また、教室で学んだ外国語を日常生活の中で使うことで、その言語の運用能力や非言語を含むコミュニケーション能力を向上させることができます。日本の国内市場の縮小を背景に、海外展開を検討・実施する企業は少なくありません。今後は、海外拠点を増やす企業や社内の国際化を進める企業がさらに増加すると予想されます。学生時代の海外経験は、そうした企業が求める国際的な人材としての素地を養い、必要なスキルを身につける実践的な機会になります。(国際学部:佐藤講師)
海外経験は、自己理解を深める貴重な経験になるという点でも、個人のキャリアにおいて価値を持つと言えます。「4年間でやりたいことを見つけたい」と考えて、大学進学を決めた人もいるでしょう。学生時代に見つけたやりたいことを卒業後の進路につなげるためには、早い段階で自分の大切な価値観や強みを把握し、キャリアの方向性を明確にすることが重要です。海外経験は、そのような自己を再認識する機会になり得ます。異なる背景を持つ人々の多様な意見に触れ、柔軟な適応力が求められる経験をすることで、新たな関心や意外な得意分野を発見するかもしれません。海外経験の期間の長短を問わず、そのように実体験で得た気づきや学びは、自分にしか手に入れられない一生の財産です。就職後のキャリアにおいても、自分を支える経験になるでしょう。(国際学部:佐藤講師)
Studying abroad offers students the unique opportunity to immerse themselves in different cultures, broadening their perspectives and enriching their understanding of the world. In today’s interconnected global society, such experiences are invaluable for both personal growth and professional development. They help students build crucial skills such as adaptability, communication, and problem-solving, which are essential in navigating diverse environments. Whether through internships, language exchange, or cultural exploration, overseas experiences enhance students' global awareness and prepare them for international careers. Furthermore, these experiences often lead to lasting connections and networks that can be instrumental in future opportunities. At the International Program, students are encouraged to embrace these opportunities to not only learn about other cultures but also develop a global mindset that will benefit them throughout their lives.(国際学部:Alexander准教授)
英米学科で何を学ぶのか?
The Department of British and American Studies offers an exceptional international learning experience that transforms how students connect with the world and the global workplace. Our curriculum goes beyond traditional language training, creating a vibrant multicultural environment where students from around the world collaborate, communicate, and cultivate international and professional skills. Through innovative programs, you'll engage with peers from diverse countries, participate in cross-cultural tasks, and develop the communication strategies essential for success in today's interconnected global work environments. Our international approach means learning extends far beyond the classroom. Students can access exchange programs, international internships, and collaborative projects with global partners in Europe, North America, and Asia. You'll develop not just language skills, but a sophisticated understanding of international business communication, workplace dynamics, and cross-cultural collaboration. Imagine learning alongside students from Japan, Korea, China, The United States, South America and Europe - all focused on building meaningful connections and understanding global and professional contexts. Our programme does not just help you learn English; it prepares you to become a confident, adaptable international professional ready to succeed in any global setting. Join us and transform your future, one international connection at a time!(国際学部:Warrington教授)
語学力を向上させるための秘訣は?
Improving one's language skills involves a multimodal approach that combines consistent practice and strategic learning techniques. But one of the secrets to language improvement is immersion. Surrounding yourself with the language you want to learn, whether through watching TV shows or movies, listening to podcasts or music, or engaging in conversations with speakers of it, can significantly enhance your comprehension and fluency. Another necessary aspect is active practice; this includes writing, speaking, and reading in the target language as much as possible. Keeping a journal, participating in language exchange programmes, or even using language learning apps can be highly beneficial. Additionally, understanding the grammatical structures and vocabulary of the language in context can help you communicate more accurately. Using flashcards, reading books or articles, and taking online or in-person courses can be effective tools for this purpose. Moreover, setting achievable goals and tracking your progress can motivate you to continue learning. However, be patient and do not be afraid of making mistakes, as they are a normal part of the learning process. By being realistic and combining these strategies with consistent effort, you can significantly improve your language skills. Consistency and persistence are key to achieving fluency!(国際学部:Warrington教授)

 過去問題
過去問題
 OPENCAMPUS
OPENCAMPUS
 入試情報
入試情報
 ネット出願
ネット出願