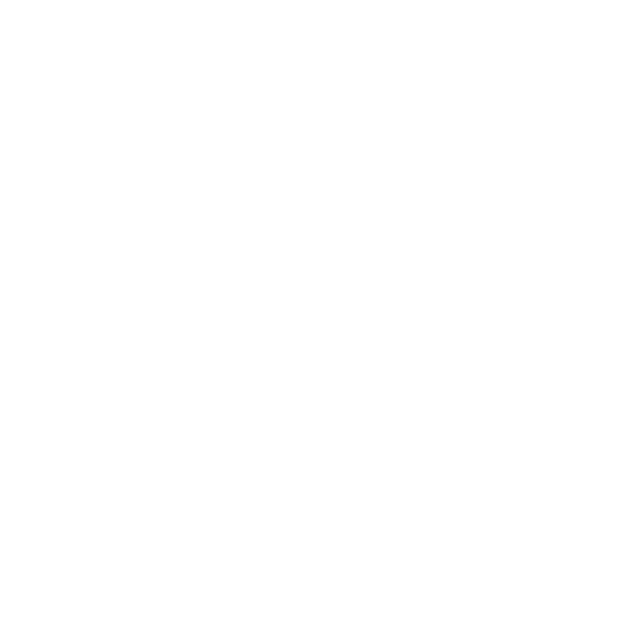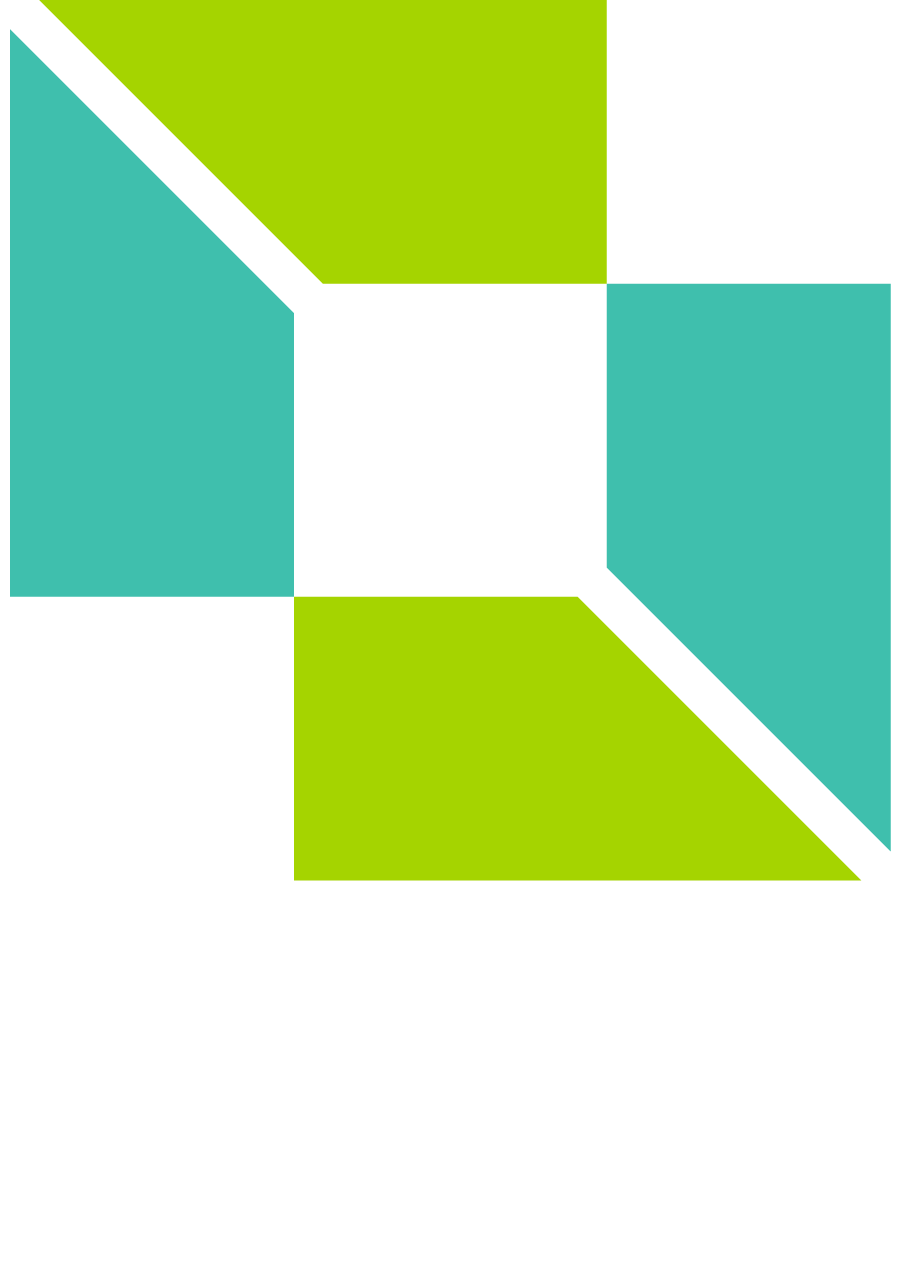インターンシップ派遣先のインドでの出会い

経営学部経営学科 2年 東間さん
静岡県立浜松商業高等学校出身
今回はインドでの長期インターンシップに挑戦した、名古屋キャンパス経営学部経営学科所属 2年の東間さんの体験をご紹介いたします。2018年3月に静岡県立浜松商業高等学校を卒業し、同年4月に名古屋キャンパスに入学しました。2年次に進級する前の春休み期間とTerm1(4,5月)を使って、長期の海外インターンシップ(通称CAPI)に参加しました。
1年次のアクティブラーニングの授業では、ビジネスに関する意思決定やコミュニケーション能力をケース通じて学び、今回の海外インターンシップでは実践力を修得することができたようです。また海外に行くことが好きで、長期の海外インターンシップを経験したことで、海外で働くことにも興味を持ち始めようでTOEICの勉強も始めているそうです。
東間さんが学内での学びと今回の体験から実践的にビジネスを学んだことは、名古屋キャンパスで取得できる学位Bachelor of Business Administration(通称BBA)の学びそのものです。
今回は、海外インターンシップで実際にどのような体験をしてきたかをお話してくれました。
名古屋商科大学では国際的な視野をもったグローバル人材を育成するために、夏期休暇中と春期休暇中の年2回海外インターンシップ(通称CAPI)を実施しています。これまでに通算694名の学生(2012年度-2019年度春)がインド・インドネシア・タイなどASEAN諸国の日系企業で海外インターンシップを体験し、名古屋キャンパスの学生ものべ33名(2016年度-2019年度春)が参加しています。
海外インターンシップで行なった仕事について教えてください。
今回の研修では日系企業がコンサルティングしている、インドにあるThe Chancery Hotelが所有している日本食レストラン「祭」で行いました。
研修内容は主にレストランスタッフの個人評価ファイルの作成、3月〜4月度の給料査定評価の資料作成、日本語教育(Speaking、Writing test、ひらがな)、5s(整理、整頓、清掃、清潔、躾)及び報連相の継続実施と癖付け、日々の業務報告書作成などを中心とし、この他にも様々な業務に携わらせていただきました。
研修以外の場面では日本での大学生活では経験できないような体験もできました。例えば派遣先企業で使用されているコミットメントシート(目標達成度を図る報告書)で自分の業務の明確な達成基準を設け、それをどう達成していくのか、その業務に対しての上司に評価してもらうという本格的な就業体験もさせていただくことができました。
またミーティングの場面では、僕の発表の際に時間を自分で指定し、その中でプレゼンをするという派遣企業ならではのやり方も体験することもできました。様々な体験から自分の足りない部分を発見することもできました。
主な業務
- レストランスタッフの個人評価ファイル作成
- 3月〜4月度の給料査定評価の資料作成
- 日本語教育(Speaking、Writing test、ひらがな)
- 5s及び報連相の継続実施と癖付け
- インド人と日本人の違いのリストを作成
- レストランスタッフ昇給制度作成
- レストランスタッフの緊急連絡網、緊急連絡表、始末書、退職するスタッフの認定証作成
- レストランスタッフのシュミレーションテスト実施
- レストランのキッチンスタッフのカレンダー作成
- レストランのキッチンスタッフの査定実施
- レストランのサービススタッフ査定表作成
- メニューやお弁当広告作成

レストランのキッチンスタッフ

レストランのサービススタッフ
海外インターンシップの経験を通じで身についたことはありますか?

研修を通して様々なことを学ぶことができました。
大きく分けると次の3つです。
1.時間の使い方と計画の立て方、主体性、行動力
2.異文化の中での仕事
3.人との出会い
名古屋キャンパスが所在する伏見という地域はビジネス街です。よって私がイメージするビジネスマンをよく目にする環境です。仕事をするということは、どんなことにもきっちりしなくてはいけないと思っていたので、この3ヶ月は自分のイメージするビジネスマンを演じてみようと思い行動しました。
初日に業務の引き継ぎを行い現場の担当の方からの課題をもらった際に、これを3ヶ月でやり遂げることができるのかととても不安に思ったことを今でも覚えています。また、「個人を評価するファイルなんてどんな風に作るんだ?」と自分がもらった課題に対してどう対処しどうこなしていけばいいのか、右も左も全くわからない状態でした。
僕の場合、デスクワークができる時間が1日平均4時間だったので少ない時間の中でこの時期までにこれを終わらせるという予定をカレンダーに書き込み行動しました。これをすることによって残りの期間にやらなければいけないことが明確化され、自分のやるべきことに集中し業務を行うことができました。最初の頃は1つの業務ばかりを考えることが必死だったのですが、日数が立つごとに慣れていき、途中に頼まれる業務を組み込みながら、自分の中で優先順位を入れ替えたりし、スムーズにこなしていくことができるようになりました。
そして主体性・行動力の面では、まず自分に任された仕事に誇りをもって取りかかると心に決め実行しました。またこの研修に行っていなければ出会うことができなかった方々から、仕事の面だけでなく「生きるということ、命、社会の歩き方」を学びました。そしてお世話になった企業の方以外にもインド在駐の大手企業の方にも出会い将来の働き方の目標を見つけることができました。
海外インターンシップに参加したことで得た「気づき」を教えてください。

インドの街並み
海外の現地企業で働くということは、その文化や考え方を理解することが大切だと気づきました。加えて、その文化を受け入れるだけでなく、自分の仕事に対する信念を持って対応する必要性も働くことで強く感じました。
インドで働いてみると、日本とは全く違うアクシデントや問題が起こることが日常茶飯事でした。それを受け止め、日本人とは感性の違う人と関わる時にはどうするとよいのか、そして遅刻や指示を守らないといったことに対しても許すという心の広さの必要性も感じました。
滞在中に海外で駐在している日本人の方々に「インド人スタッフとどういう風に接し、指導をしていますか?」と質問しました。色んな人が共通して言うことは、5sと報連相といった日本のビジネスマンの当たり前のこと、そして今までの自分のやり方を変えないということでした。国が違うからといって仕事に対しての信念を曲げないことが大切だと理解できました。
このように様々な企業で働く方の考え方を感じられたのは、日本人が多く利用するホテルでのインターンシップだったからこそだと思います。自分が想像していた以上に人との関わり、普通に大学生活を送っていただけではできないコネクションが気づいたらできていました。人との出会いは主体性と行動力が必要だと思います。何事にも責任と自覚を持って行動できたことと、このような素晴らしい出会いからも成長を感じられました。
この経験をこれからの大学生活にどのように活かしていきたいですか?
これからは、時間的な効率を考え行動するようにしたいと思っています。
大学では毎日違う授業を受けるのでそれぞれ考えることが違うけれど、仕事は毎日の連続なので次の日のことを考え動くよう意識していました。
なので、今までの私は授業の前日にレポートを書くことに頑張りすぎてしまい寝るのが遅くなることも1年次はよくありました。しかし、それは当日の授業への集中力が途切れてしまう原因だったと思います。
そんな無駄な時間を減らすために、授業が休みの土日月のうちに1週間分のレポートを前もってやり計画性持って予習していこうと考えています。
今回のインドで出会った方から「整理整頓できる人は仕事ができる」と聞き、物を捨てられない自分が変わったことも変化のひとつです。
今は、将来どんな仕事につきたいというのはありません。今回のインターンシップに言った理由もどんな仕事があるか知るために参加しました。ただ、海外に出たいという夢は高校の時からあったので、今回の体験を通じて海外に行きたいではなく「海外で働きたい」と思うようになりました。
海外駐在するにはTOEICの勉強も必要だろうと思い学習し始めています。私は体験を通じて気づくタイプなのでこれからも多くの経験をしていきたいと思っています。
取材:2019年5月

 過去問題
過去問題
 イベント
イベント
 入試情報
入試情報
 ネット出願
ネット出願